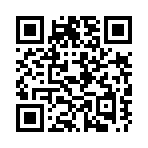この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。
詳しい説明は難しいので画像を中心に載せておきます。
(3)運転しやすい牽引機構









・キャビンの荷重は補助輪にかける:平行に保つためキャビン重量の一部を支えることになるキャビン前部のアームが、補助輪2輪をつなげるサブフレームを抑える形とすることでキャビン重量は牽引自転車にかかることなく牽引しやすくなる。補助輪と補助輪のサブフレームがキャビンにつながると、牽引自転車なくとも構造上4輪となり安定する。
・補助輪は牽引車両後輪と同軸の左右に配置:補助輪を牽引自転車後輪と同軸に配置することで、牽引自転車の前輪ハンドルをまげて右左折の動作をする時にその動作に同期して転回を容易にする。
・路面の傾きに対応し補助輪と牽引車両のねじれに対応する(上下左右):牽引自転車のヘッド付近において、補助輪のサブフレームをバンドなど強度を持つ柔軟な部材で固定することにより、補助輪と牽引車両がねじれても対応できるものとする。そしてもう一点サドル付近で上下動は可動としながらも左右動を抑えることで、牽引自転車と補助輪との平行を保つ。また、ねじれが過ぎると牽引自転車のペダルその他の部分が補助輪と接触するので、軸同士を別のベルトでつなぐことにより可動範囲は一定範囲に規制する。
・路面の傾きに対応し牽引車両とキャビンのねじれに対応する(上下左右):キャビン前部のアームをねじれ方向に可動とすることで、路面の傾きなどで補助輪とキャビンとがねじれの関係になっても車輪が浮くことなく地面に密着して安定を保つことができる。
・牽引車両とキャビンは結接部で自由に屈曲し転回に追従する:補助輪2輪をつなげるサブフレームとキャビン前部のアームが結接する部分は、地面に垂直となる方向を軸に回転可能な構造とする。このことで補助輪2輪を含む牽引車両とキャビンは結接部分で180°以上自由に屈曲し、全長が3.5m前後の車両が幅2.5m程度の回転半径にて転回可能となる。
・重さを感じないギヤ比(現在導入作業中):外装式変速機と内装式変速機を組み合わせることにより、通常の自転車よりもはるかに幅広い変則域を可能とする。
(3)運転しやすい牽引機構









・キャビンの荷重は補助輪にかける:平行に保つためキャビン重量の一部を支えることになるキャビン前部のアームが、補助輪2輪をつなげるサブフレームを抑える形とすることでキャビン重量は牽引自転車にかかることなく牽引しやすくなる。補助輪と補助輪のサブフレームがキャビンにつながると、牽引自転車なくとも構造上4輪となり安定する。
・補助輪は牽引車両後輪と同軸の左右に配置:補助輪を牽引自転車後輪と同軸に配置することで、牽引自転車の前輪ハンドルをまげて右左折の動作をする時にその動作に同期して転回を容易にする。
・路面の傾きに対応し補助輪と牽引車両のねじれに対応する(上下左右):牽引自転車のヘッド付近において、補助輪のサブフレームをバンドなど強度を持つ柔軟な部材で固定することにより、補助輪と牽引車両がねじれても対応できるものとする。そしてもう一点サドル付近で上下動は可動としながらも左右動を抑えることで、牽引自転車と補助輪との平行を保つ。また、ねじれが過ぎると牽引自転車のペダルその他の部分が補助輪と接触するので、軸同士を別のベルトでつなぐことにより可動範囲は一定範囲に規制する。
・路面の傾きに対応し牽引車両とキャビンのねじれに対応する(上下左右):キャビン前部のアームをねじれ方向に可動とすることで、路面の傾きなどで補助輪とキャビンとがねじれの関係になっても車輪が浮くことなく地面に密着して安定を保つことができる。
・牽引車両とキャビンは結接部で自由に屈曲し転回に追従する:補助輪2輪をつなげるサブフレームとキャビン前部のアームが結接する部分は、地面に垂直となる方向を軸に回転可能な構造とする。このことで補助輪2輪を含む牽引車両とキャビンは結接部分で180°以上自由に屈曲し、全長が3.5m前後の車両が幅2.5m程度の回転半径にて転回可能となる。
・重さを感じないギヤ比(現在導入作業中):外装式変速機と内装式変速機を組み合わせることにより、通常の自転車よりもはるかに幅広い変則域を可能とする。
晴れたり曇ったりしながらも雪はまだ降っており、除雪があるおかげでMTBではなんとか走れますが、普通の自転車では移動は困難です。こう言う日はゆっくりと中での作業に適しています。今日も引き続きリキシャの構造の詳細を書きます。
(2)転倒防止機構
・牽引車両に転倒防止の補助輪を設ける:牽引車両が通常の2輪の自転車だと、当然横倒れになる可能性がある。牽引車両が横倒れになると後のキャビンもつられて前のめりになり、乗客は非常に危険な思いをすることになる。このような状態を避けるため、牽引車両には補助輪を設け、倒れないようにする。またこの補助輪は後のキャビンの重量を支える役割も果たす。キャビンの自重と乗られるお客さまの重量を加えると相当の重量となる。キャビンの車輪と補助輪の4輪で重量を支える。キャビンの重量が牽引する自転車に乗っからず、補助輪が受けてくれることにより操縦安定性も高まる。またストッパーやパーキングブレーキを設け、乗務員が側にいないときに車両の動きを固定する。
<参考寸法③>補助輪車輪/キャビン車輪
彦根リキシャ 20×1.75/2.25-17(子どもMTB前輪とカブ用の前輪を流用)
長&戦&竹 26×1.75/26×1.75(MTBの前輪を流用)




youtubeに動画をアップしておきました。
http://youtu.be/roQ2y3HA-dQ
(2)転倒防止機構
・牽引車両に転倒防止の補助輪を設ける:牽引車両が通常の2輪の自転車だと、当然横倒れになる可能性がある。牽引車両が横倒れになると後のキャビンもつられて前のめりになり、乗客は非常に危険な思いをすることになる。このような状態を避けるため、牽引車両には補助輪を設け、倒れないようにする。またこの補助輪は後のキャビンの重量を支える役割も果たす。キャビンの自重と乗られるお客さまの重量を加えると相当の重量となる。キャビンの車輪と補助輪の4輪で重量を支える。キャビンの重量が牽引する自転車に乗っからず、補助輪が受けてくれることにより操縦安定性も高まる。またストッパーやパーキングブレーキを設け、乗務員が側にいないときに車両の動きを固定する。
<参考寸法③>補助輪車輪/キャビン車輪
彦根リキシャ 20×1.75/2.25-17(子どもMTB前輪とカブ用の前輪を流用)
長&戦&竹 26×1.75/26×1.75(MTBの前輪を流用)




youtubeに動画をアップしておきました。
http://youtu.be/roQ2y3HA-dQ
冷えるが晴れた太陽も顔を出す一日となりました。風は少し強いようですが。
リキシャの製作に関しては本当に色々な方にお世話になって今まで作ってくることが出来たので、この詳細の部分をきちんと公開したいと思います。同じように作る方がある場合の参考にして頂けたらとも思います。以下にも書きますが、色々試作したり、知人友人に試乗してもらったり、専門家の意見を聞いてみた上で、構造や寸法を決めることができました。基本的な寸法は別として、デザインはデザイナーにお願いすることも大いに有効であったように思います。
機構と形状の詳細
(1)キャビン
<参考寸法①>H:全高㎜、L:全長㎜、W:全幅㎜(客室部分のみ牽引部のアームは除く)
※ 彦:彦根リキシャ、長:長浜リキシャ、戦:戦国リキシャ、竹:竹リキシャ
彦 H: (1960)㎜ L:(1190)㎜ W:1146㎜ 屋根は銅版葺き、塩ビシートで防寒
長 H: (1875)㎜ L: (1200)㎜ W:1210㎜ 屋根は板葺き、PC板などで防寒
戦 H: (1700)㎜ L: (1120)㎜ W:1100㎜ 屋根は木とPCの板、PC板などで防寒
竹 H: (1900)㎜ L: (1370)㎜ W:1100㎜ 屋根は編んだ竹、
・屋根と壁:試作段階では屋根のない壁もない、椅子だけのものを作ってみたが、試しに乗って頂く多くの方から、雨風はしのげた方がよいという声が多く、屋根と壁がある構造を標準とした。またあまりにもオープンだと恥ずかしいとか、不安を感じるという声もあった。ただ夏の開放感は必要で、周りの視線や暑い日ざしが直接当たらない程度に、夏は取り外しできる薄いプラスチック板と日除けの簾を組み合わせた。また運転手とのコミュニケーションのため、前方を覆う部分も一部空けた状態で声がお互いに聞こえる程度とした。



・乗り込み口:乗り込み口が牽引する自転車に邪魔にならないように後ろ向きに乗るものを一番最初に作ってみたが、多くの方が「進行方向が見えないと不安で怖い」との感想を挙げたので、前か横が入口で前向きに座る形を採用した。



・幅広さ:幅広さは大人2人と子ども1人が座る座面ができるだけ広く、かつ外形幅がコンパクトに収まる寸法を選択した。この際座る位置が低いと重量を支える車輪が座面に出っ張る形になるので、この部分をひじ置きにするなどの対処を施した(重量を支えるのに十分なサイズの車輪を座面下に収めようとすると座面が高くなる)。



・高さ:天井高さは乗り降りするのに邪魔にならない程度に低く、かつ座った状態で外を眺める時開放感のある高さを心がけた。高くなりすぎると重心も高く不安定となるし風であおられたりもするので、できる限りにおいて低くするよう心がけた(人力で引っ張るので風の抵抗の大小はとても大きい)。
・椅子の位置と角度:色々試した結果、深く腰掛ける形が安定するが、ご年配の方はあまり深いと次に立ち上がるときに立ち上がりにくいという声があったため、キッチンの椅子よりは低く、ソファよりは高い辺りの位置に収めた。乗客が乗車中に前後左右に移動されてしまうと、位置の変動が運転しづらさとなってしまうので、座るとある位置に定着するような形状を心がけた。
・地元に根ざしたデザイン:ある程度目立たないと危険であるし、気にもかけていただけないので存在感は必要であるが、乗ると恥ずかしいと感じるようなものはよくない。ぎりぎりのラインで、地域特有の様式を盛り込んだデザインなら少し派手でも乗客は納得して頂きやすいであろうという配慮からも、地域にあった形を盛り込んで頂くようお願いした。実際、観光客の方は比較的派手なデザインでも旅先と言うことで喜んで乗っていただけるが、福祉目的で利用される地元のおばあちゃん達は、しばらくの期間走り回って自転車タクシーが街になじむまでは恥ずかしそうにされる姿が見受けられた。以下、各地のリキシャはそれぞれデザイナーに協力を仰いだ。
☆彦根リキシャ:滋賀県立大学印南研究室(および大工:三木君)
☆長浜リキシャ:キャビン製作者に同じ(片山木工)
☆八幡竹リキシャ:松田栄一氏
☆戦国リキシャ:立澤竜也氏
リキシャの製作に関しては本当に色々な方にお世話になって今まで作ってくることが出来たので、この詳細の部分をきちんと公開したいと思います。同じように作る方がある場合の参考にして頂けたらとも思います。以下にも書きますが、色々試作したり、知人友人に試乗してもらったり、専門家の意見を聞いてみた上で、構造や寸法を決めることができました。基本的な寸法は別として、デザインはデザイナーにお願いすることも大いに有効であったように思います。
機構と形状の詳細
(1)キャビン
<参考寸法①>H:全高㎜、L:全長㎜、W:全幅㎜(客室部分のみ牽引部のアームは除く)
※ 彦:彦根リキシャ、長:長浜リキシャ、戦:戦国リキシャ、竹:竹リキシャ
彦 H: (1960)㎜ L:(1190)㎜ W:1146㎜ 屋根は銅版葺き、塩ビシートで防寒
長 H: (1875)㎜ L: (1200)㎜ W:1210㎜ 屋根は板葺き、PC板などで防寒
戦 H: (1700)㎜ L: (1120)㎜ W:1100㎜ 屋根は木とPCの板、PC板などで防寒
竹 H: (1900)㎜ L: (1370)㎜ W:1100㎜ 屋根は編んだ竹、
・屋根と壁:試作段階では屋根のない壁もない、椅子だけのものを作ってみたが、試しに乗って頂く多くの方から、雨風はしのげた方がよいという声が多く、屋根と壁がある構造を標準とした。またあまりにもオープンだと恥ずかしいとか、不安を感じるという声もあった。ただ夏の開放感は必要で、周りの視線や暑い日ざしが直接当たらない程度に、夏は取り外しできる薄いプラスチック板と日除けの簾を組み合わせた。また運転手とのコミュニケーションのため、前方を覆う部分も一部空けた状態で声がお互いに聞こえる程度とした。


・乗り込み口:乗り込み口が牽引する自転車に邪魔にならないように後ろ向きに乗るものを一番最初に作ってみたが、多くの方が「進行方向が見えないと不安で怖い」との感想を挙げたので、前か横が入口で前向きに座る形を採用した。

・幅広さ:幅広さは大人2人と子ども1人が座る座面ができるだけ広く、かつ外形幅がコンパクトに収まる寸法を選択した。この際座る位置が低いと重量を支える車輪が座面に出っ張る形になるので、この部分をひじ置きにするなどの対処を施した(重量を支えるのに十分なサイズの車輪を座面下に収めようとすると座面が高くなる)。



・高さ:天井高さは乗り降りするのに邪魔にならない程度に低く、かつ座った状態で外を眺める時開放感のある高さを心がけた。高くなりすぎると重心も高く不安定となるし風であおられたりもするので、できる限りにおいて低くするよう心がけた(人力で引っ張るので風の抵抗の大小はとても大きい)。
・椅子の位置と角度:色々試した結果、深く腰掛ける形が安定するが、ご年配の方はあまり深いと次に立ち上がるときに立ち上がりにくいという声があったため、キッチンの椅子よりは低く、ソファよりは高い辺りの位置に収めた。乗客が乗車中に前後左右に移動されてしまうと、位置の変動が運転しづらさとなってしまうので、座るとある位置に定着するような形状を心がけた。
・地元に根ざしたデザイン:ある程度目立たないと危険であるし、気にもかけていただけないので存在感は必要であるが、乗ると恥ずかしいと感じるようなものはよくない。ぎりぎりのラインで、地域特有の様式を盛り込んだデザインなら少し派手でも乗客は納得して頂きやすいであろうという配慮からも、地域にあった形を盛り込んで頂くようお願いした。実際、観光客の方は比較的派手なデザインでも旅先と言うことで喜んで乗っていただけるが、福祉目的で利用される地元のおばあちゃん達は、しばらくの期間走り回って自転車タクシーが街になじむまでは恥ずかしそうにされる姿が見受けられた。以下、各地のリキシャはそれぞれデザイナーに協力を仰いだ。
☆彦根リキシャ:滋賀県立大学印南研究室(および大工:三木君)
☆長浜リキシャ:キャビン製作者に同じ(片山木工)
☆八幡竹リキシャ:松田栄一氏
☆戦国リキシャ:立澤竜也氏
昨日は雨で、朝少し冷えるなと思ったら山のほうは白くなっていました。昼に風が吹き、今は雪がちらつき時折あられも降っている様子です。こんな日は割っておいたマキが今日は活躍しそうです。タイトルとは関係ありませんが、近所の方が積み上げたマキが美しかったので写真をとりました・・・。以下リキシャの機構詳細です。

構造と形状のデザインの考え方
自転車に人を載せるにあたり、その環境的な意味や福祉的な意味を考えると、体力と気力のあるものは普通自転車を自分でこいで走ればいいと考え、メインターゲットからは外して考えた。動けない、または動きにくい人をスムースに自転車タクシーに載せてあげたいと考えた。家族や同伴者が一緒に乗ることができる、大人2人と子ども1人を一緒に載せたいと考えた。気候条件の厳しいときこそ楽のできる乗り物にしたいと考えた。そして乗りたくなるような、安心感のある、格好のいいデザインが必要と考えた(観光用となっている人力車をイメージするとわかりやすい)。特に彦根においてはお城とその周りの城下町に特徴があり、その雰囲気に調和する外見と内装が必要と考えた(長浜や近江八幡のリキシャにも同様に考えた)。以下に考え方を箇条書きとしてまとめた。
・大人2人と子ども1人が深く腰かけられて安定する座席を有する。
・暑さ寒さや雨風を遮る屋根や壁、もしくはシートを有する。
・体が不自由な方でも乗りやすい低床で、つかみやすい持ち手がある。
・乗降時にも走行中にも倒れない、安定した機構。
・走る街に似合うデザインとする。
(彦根リキシャにおいては彦根城と駕籠をイメージした)
(長浜リキシャにおいては曳山をイメージした)
(竹リキシャにおいても町に溶け込むデザインを考えた)
また引き続き投稿したいと思います。
※戦国リキシャを幾箇所か改修しました。座高の高い方が天井に頭をぶつけるということがありましたので、天井を支える板の中心をえぐってみました。


構造と形状のデザインの考え方
自転車に人を載せるにあたり、その環境的な意味や福祉的な意味を考えると、体力と気力のあるものは普通自転車を自分でこいで走ればいいと考え、メインターゲットからは外して考えた。動けない、または動きにくい人をスムースに自転車タクシーに載せてあげたいと考えた。家族や同伴者が一緒に乗ることができる、大人2人と子ども1人を一緒に載せたいと考えた。気候条件の厳しいときこそ楽のできる乗り物にしたいと考えた。そして乗りたくなるような、安心感のある、格好のいいデザインが必要と考えた(観光用となっている人力車をイメージするとわかりやすい)。特に彦根においてはお城とその周りの城下町に特徴があり、その雰囲気に調和する外見と内装が必要と考えた(長浜や近江八幡のリキシャにも同様に考えた)。以下に考え方を箇条書きとしてまとめた。
・大人2人と子ども1人が深く腰かけられて安定する座席を有する。
・暑さ寒さや雨風を遮る屋根や壁、もしくはシートを有する。
・体が不自由な方でも乗りやすい低床で、つかみやすい持ち手がある。
・乗降時にも走行中にも倒れない、安定した機構。
・走る街に似合うデザインとする。
(彦根リキシャにおいては彦根城と駕籠をイメージした)
(長浜リキシャにおいては曳山をイメージした)
(竹リキシャにおいても町に溶け込むデザインを考えた)
また引き続き投稿したいと思います。
※戦国リキシャを幾箇所か改修しました。座高の高い方が天井に頭をぶつけるということがありましたので、天井を支える板の中心をえぐってみました。

雪の降る季節となり、リキシャも走行で忙しい時期ではないので、点検したり修理したりする期間となります。こんな時期にしかまとめられない事もあるので、機構の詳細などご紹介していこうと思います。
「リキシャ作成」の意図
クルマに代わる交通手段として自転車は高い性能を持つ(雨風や暑さ寒さなどの気候条件の悪いときは工夫が必要ではあるが)。また2輪の車体は不安定だが、後ろに車両を牽引する牽引車両に載せると、安定して荷物や人を運ぶことができる。牽引車両として、日本では古くからリヤカーが活躍しているし、西洋ではサイクルトレーラーまたはキッズトレーラーとして子どもを載せる運搬具が活躍している。
荷物だけでなく、子どもだけではなく、大人を複数のせて、タクシーより気軽な運搬手段として、自転車の「自転車タクシー」としての活用を意図した。実際は日常において自転車タクシーの必要性は極めて低い。ほとんどの人にとっての日常生活上の移動は普通自転車と公共交通機関の組み合わせで事が足りる(現実はクルマの利用がほとんどであるが)。荷物もほとんどの場合、既存のリヤカーがあれば十分運べる(現実はクルマの利用がほとんどであるが)。しかしながら「環境負荷の低い」「今はない新しい文化」を作る必要性を感じ、わずかな需要ではあるが「観光用」や「福祉用」としての用途を念頭において、極端な形ではあるが自転車を活用するスタイルをPRするという意図も含めて、自転車タクシー「リキシャ」を製作するに至った。
以下の写真は整備と補強のため頭を残してストリップ?にした戦国リキシャです。ツノだけ残しております。よく働きましたので、次の春に備え、壊れている訳ではないですが、補強とより乗りやすくする改修を行っております。

「リキシャ作成」の意図
クルマに代わる交通手段として自転車は高い性能を持つ(雨風や暑さ寒さなどの気候条件の悪いときは工夫が必要ではあるが)。また2輪の車体は不安定だが、後ろに車両を牽引する牽引車両に載せると、安定して荷物や人を運ぶことができる。牽引車両として、日本では古くからリヤカーが活躍しているし、西洋ではサイクルトレーラーまたはキッズトレーラーとして子どもを載せる運搬具が活躍している。
荷物だけでなく、子どもだけではなく、大人を複数のせて、タクシーより気軽な運搬手段として、自転車の「自転車タクシー」としての活用を意図した。実際は日常において自転車タクシーの必要性は極めて低い。ほとんどの人にとっての日常生活上の移動は普通自転車と公共交通機関の組み合わせで事が足りる(現実はクルマの利用がほとんどであるが)。荷物もほとんどの場合、既存のリヤカーがあれば十分運べる(現実はクルマの利用がほとんどであるが)。しかしながら「環境負荷の低い」「今はない新しい文化」を作る必要性を感じ、わずかな需要ではあるが「観光用」や「福祉用」としての用途を念頭において、極端な形ではあるが自転車を活用するスタイルをPRするという意図も含めて、自転車タクシー「リキシャ」を製作するに至った。
以下の写真は整備と補強のため頭を残してストリップ?にした戦国リキシャです。ツノだけ残しております。よく働きましたので、次の春に備え、壊れている訳ではないですが、補強とより乗りやすくする改修を行っております。